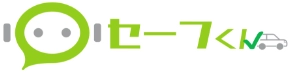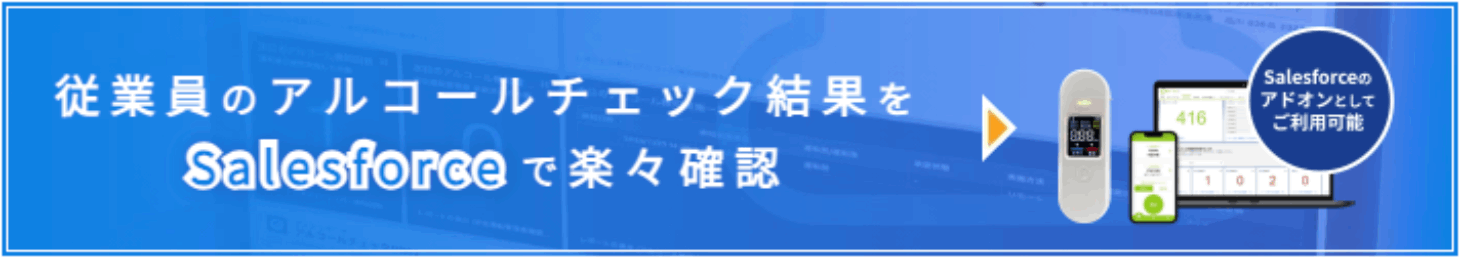アルコールチェック義務化では、運転前後1日2回の実施と8項目の記録保存が必須です。クラウドシステムを活用すれば運転日報と一元管理でき、法令遵守と業務効率化を同時に実現できます。
本記事では、義務化の基本内容から必須記録項目、効果的な管理方法まで詳しく解説します。クラウド型管理システムの活用事例や、よくある質問への回答もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください
目次
アルコールチェック義務化の基本
 2023年12月1日から道路交通法の改正により、事業所でのアルコールチェックが新たに義務化されました。酒気帯び運転の撲滅と、交通安全の確保が義務化の目的です。
2023年12月1日から道路交通法の改正により、事業所でのアルコールチェックが新たに義務化されました。酒気帯び運転の撲滅と、交通安全の確保が義務化の目的です。
ここでは、アルコールチェック義務化における基本的な情報を解説します。
アルコールチェック義務化の対象事業者
白ナンバーの車両を5台以上保有する、あるいは乗車定員11人以上の車両を1台でも持つ事業所がアルコールチェック義務の対象です。営業用や業務用、それぞれ自家用車両を業務利用している場合も該当します。
安全運転管理者を選任している企業では、改定内容への対応が不可欠です。毎日の活動の中で、社用車を使う事業者も広く含まれています。
アルコールチェック義務化の規定内容
運転前後で、1日2回の酒気帯び有無確認が全事業者で必須です。2023年12月以降は、アルコール検知器を使った測定と、記録簿へ詳細内容を記載することが義務となっています。
検査方法は直接対面だけでなく、カメラやモニターを活用した非対面方式も認められています。記録簿には運転者氏名や日時、車両番号など8項目を網羅し1年保存しなければなりません。
アルコールチェック未実施によるリスクと罰則
アルコールチェック未実施や記録不備がある場合、道路交通法違反として行政処分や罰金等の罰則が科されます。安全運転管理者の選任取消しや、事業所への監督指導が行われる可能性も高まるため注意が必要です。
他にも、違反企業は社会的信用の大幅な低下や、商取引契約解除など経営への直接的な影響を受ける場合もあります。企業イメージの悪化にも直結するため、予防と遵守体制の構築が重要です。
関連記事:【2025年最新】アルコールチェックが義務化!対象者や企業がとるべき対策を解説
アルコールチェック義務化による運転日報とは
 運転日報は車両ごとの運行経路や使用時間などを記録し、業務管理や安全確認を目的として作成される書類です。アルコールチェック記録簿は酒気帯びの有無を確認する記録ですが、改正道路交通法により両方の項目を1つにまとめるケースが増えています。
運転日報は車両ごとの運行経路や使用時間などを記録し、業務管理や安全確認を目的として作成される書類です。アルコールチェック記録簿は酒気帯びの有無を確認する記録ですが、改正道路交通法により両方の項目を1つにまとめるケースが増えています。
運転日報は業務や運行管理が中心となり、アルコールチェック記録は酒気帯び有無の法令遵守に直結しています。混同による管理の曖昧化を防ぐため、目的ごとの記載内容の理解と運用が重要です。
出典:道路交通法施行規則 第九条の十(昭和三十五年総理府令第六十号)|e-GOV
アルコールチェック義務化による記録簿と運転日報の必須項目
 アルコールチェック義務化に伴い、運転日報とアルコールチェック記録簿の記載項目が法令で明確に定められています。それぞれの記録簿に記載する必須項目は以下の通りです。
アルコールチェック義務化に伴い、運転日報とアルコールチェック記録簿の記載項目が法令で明確に定められています。それぞれの記録簿に記載する必須項目は以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 運転者の氏名 | 実際に運転業務を担当した人物の特定に用いる |
| 運転の開始・終了日時 | 運行の開始時刻と終了時刻を記録し、労務管理や業務把握に活用する |
| 運転した距離 | 当日車両が走行した総距離を数値で記録し、安全管理や経費把握に役立つ |
| その他必要な事項 | 行き先や運行目的、休憩時間など企業ごとに必要な内容を追加で記載する |
| 項目 | 概要 |
| 確認者氏名 | アルコールチェックを担当する安全運転管理者などの氏名を記録する |
| 運転者氏名 | チェック対象となる運転者の氏名を明確にする |
| 確認日時 | チェックを実施した日時を記録し、履歴管理に利用する |
| 車両番号 | 対象となる車両を識別するための番号や記号を記載する |
| 確認の方法 | 対面・非対面、アルコール検知器の有無など計測方法を記録する |
| 酒気帯びの有無 | 運転者の酒気帯び状態について結果を記録する |
| 検知器の表示数値 | アルコール検知器で計測された具体的な数値を記録する |
| その他必要な事項 | 追加で指示事項や特記事項があればその内容も含めて記載する |
各記録は法令遵守の証拠として1年間保存が義務付けられており、監査時の重要な書類となります。記録項目の漏れや記載ミスは法令違反につながるため、企業は記録管理をしっかりと行うための準備が必要です。
関連記事:アルコールチェックの記録簿とは?記載や保管方法からテンプレートまでをご紹介
関連記事:記録機能付きアルコールチェッカーのおすすめ人気ランキング14選
アルコールチェック義務化による運転日報のおすすめ記録方法
 手作業による記録ミスを防ぐためにも、管理者負担を軽減する仕組み構築が求められています。アルコールチェックの記録や運転日報を、効率よく管理するための方法を3つご紹介します。業務フロー改善により、法令違反リスクを回避できます。
手作業による記録ミスを防ぐためにも、管理者負担を軽減する仕組み構築が求められています。アルコールチェックの記録や運転日報を、効率よく管理するための方法を3つご紹介します。業務フロー改善により、法令違反リスクを回避できます。
1. 目的別に合わせてテンプレートを使用する
業種や事業規模に応じた運転日報テンプレート活用により、記録漏れや記載ミスを大幅に削減できます。無料ダウンロード可能なテンプレートを活用すれば、導入コストを抑制しながら法令対応が可能です。
記入例付きのフォーマットなら初回導入時の混乱も最小限に抑えられます。各企業の運用実態に合わせたカスタマイズも容易であり、継続的な改善と最適化が図れます。
2. 電子媒体で管理
紙ベースの記録管理から電子媒体への移行により、データ検索性向上や保管スペース削減などの効果が得られます。クラウド保存により、遠隔地からのアクセスや複数拠点での情報共有も、円滑に進めることが可能です。
改ざん防止や履歴管理機能が備わっていれば、記録の信頼性と透明性が確保されます。監査対応時の資料提出や集計作業も、大幅に効率化できる点もメリットです。
3. アルコールチェックの記録や勤怠記録と一元管理
アルコールチェックや運転日報、勤怠記録を個別管理すると手作業増加によりミスや不正のリスクが高まります。一元管理システムを導入すれば業務効率が向上し、管理者負担を最小限に抑えられます。
手入力削減や記録自動化、法令遵守強化などが同時に実現する点もメリットです。統合管理により、安全で効率的な運行管理体制を構築し、企業のコンプライアンス強化にもつながります。
記録を一元管理し、効率よく保管できるクラウド型アルコールチェッカー「セーフくん」
 セーフくんは、運転日報とアルコールチェック記録の一元管理に特化したクラウド型アルコールチェックサービスです。直感的な操作画面により、管理者と運転者双方の業務負担を大幅に軽減します。
セーフくんは、運転日報とアルコールチェック記録の一元管理に特化したクラウド型アルコールチェックサービスです。直感的な操作画面により、管理者と運転者双方の業務負担を大幅に軽減します。
リアルタイムでの記録確認と自動集計機能により、監査対応や報告書作成も効率化することが可能です。改ざん防止機能とセキュリティ対策で、企業の重要データを安全に保護します。
導入企業では、記録業務時間の大幅短縮と管理精度向上を同時に達成しています。効率よくアルコールチェックを行いたい企業様は、ぜひご活用ください。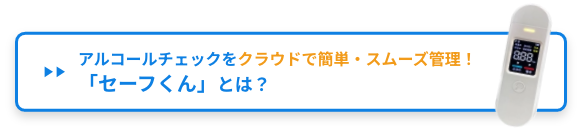
アルコールチェックの記録や運転日報を作成する際の注意点
 アルコールチェックと運転日報は法令遵守のため正確な記録が不可欠であり、記録不備はコンプライアンス違反につながります。記録作成時に注意すべきポイントは、以下の通りです。
アルコールチェックと運転日報は法令遵守のため正確な記録が不可欠であり、記録不備はコンプライアンス違反につながります。記録作成時に注意すべきポイントは、以下の通りです。
- 法定8項目(確認者・運転者名、実施日時、検知器数値など)を漏れなく記載する
- 目視確認とアルコール検知器測定結果を正確に記載する
- 改ざん防止を考慮した適切な管理体制を構築する
- 1年間保存義務に対応した安全な保管方法を選択する
- 記録の信頼性と透明性を確保する
紙ベース管理では手間と紛失リスクが高いため、アプリやクラウドシステム活用による一元管理が推奨されます。正確で確実な記録・保存体制を構築し、継続的なコンプライアンス維持を実現することが重要です。
アルコールチェックの記録や運転日報、勤怠記録はクラウドで一元管理がおすすめ
 クラウドサービスを活用すれば、アルコールチェック結果が自動的に運転日報や勤怠記録として反映され、手入力作業が不要となります。AI顔認証やGPS機能による本人確認で不正を防ぎ、厳格なコンプライアンス体制を構築できます。
クラウドサービスを活用すれば、アルコールチェック結果が自動的に運転日報や勤怠記録として反映され、手入力作業が不要となります。AI顔認証やGPS機能による本人確認で不正を防ぎ、厳格なコンプライアンス体制を構築できます。
記録は安全なクラウド上に保存されるため保管場所の心配もなく、法令で定められた1年間の保存義務にも対応可能です。複数拠点での情報共有や監査対応も効率化され、企業全体のリスク管理強化につながります。
クラウド型アルコールチェッカー「セーフくん」なら、法令遵守と業務効率化を同時に実現できます。
アルコールチェックをクラウドで簡単・スムーズ管理「セーフくん」とは?
関連記事:【2025年最新版】クラウド型アルコールチェッカーのおすすめ21選!サービス比較や選び方の解説付き
アルコールチェックの記録や運転日報のよくある質問
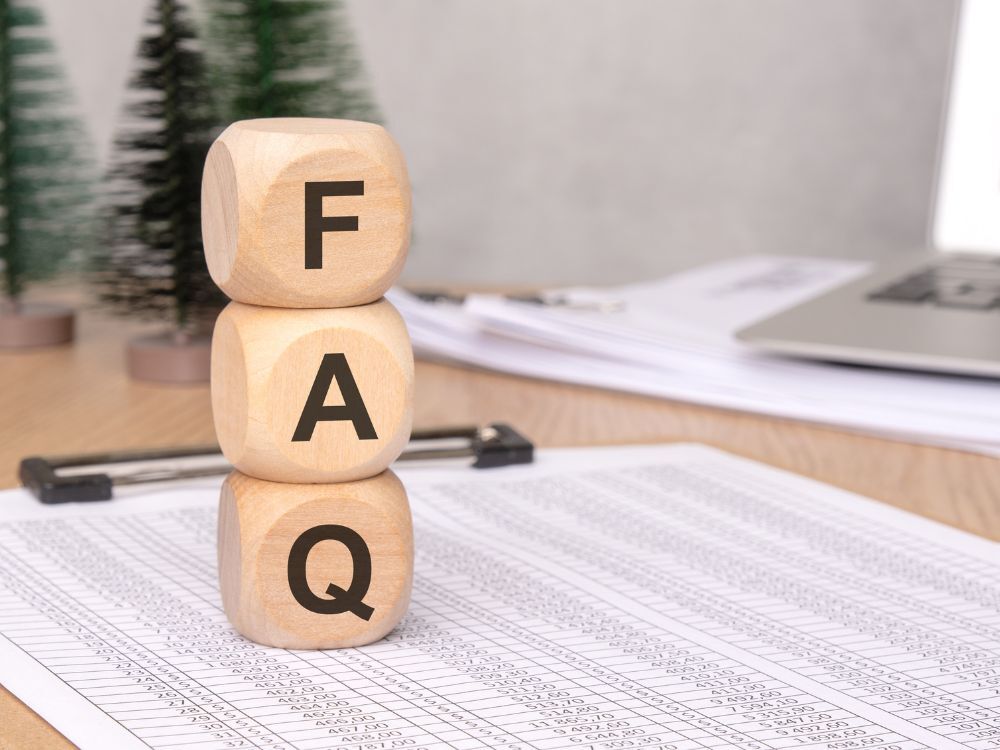 ここでは、アルコールチェックの記録や運転日報のよくある質問について、以下の項目別で回答します。
ここでは、アルコールチェックの記録や運転日報のよくある質問について、以下の項目別で回答します。
Q. 業務委託は記録の対象になりますか?
- 業務委託契約における運転者は原則として、アルコールチェック記録の義務対象外です。委託先企業が独自に安全管理責任を負う形となります。ただし安全管理の観点から、委託先に対してもアルコールチェック実施を求めることが推奨されています。委託契約における責任の所在を明確化し、安全運転に関する取り決めを契約書に記載することで予防的な対策が可能です。
Q. 直行直帰の社員はどう対応すればよいですか?
- 直行直帰勤務の社員に対してもアルコールチェック義務は適用され、営業所等への出社を伴わない場合でも実施が必要です。非対面での確認方法として、カメラやモニター、電話等を通じた遠隔確認が認められています。スマートフォンアプリやクラウドシステム活用により、自宅や現場からリアルタイムでのアルコールチェックが可能です。安全運転管理者は遠隔地からでも運転者の状態を把握し、記録を管理する責任があります。
関連記事:直行直帰時のアルコールチェックを6つの運用ステップとともに解説!
Q. 記録や作成を怠った場合どうなりますか?
- アルコールチェック記録の未作成や保存不備は、安全運転管理者の義務違反に該当し、道路交通法に基づく行政処分や罰則の対象です。記録簿保存を怠った場合、企業は監督官庁からの指導や処分を受ける可能性があります。従業員の飲酒運転リスクが高まると、企業の社会的信用失墜や取引先からの信頼低下につながります。事故発生時には民事責任や刑事責任を問われ、損害賠償請求や企業イメージの悪化につながるため注意が必要です。
Q. 記録するためのアルコール検知器に指定はありますか?
- アルコール検知器は法令による特定機種の指定はありませんが、正確な測定と適切な保守管理が可能な製品を選定する必要があります。検知器の機能や測定方式、保守性能には大きな違いがあるため、目的や優先順位に合わせた選択が重要です。呼気式や接触式など、測定方法の違いやデータ保存機能、クラウド連携機能の有無も選定の重要な判断基準となります。企業規模や使用頻度、予算に応じて最適な機種を検討しましょう。
詳細な機種比較や選定方法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:【2025年最新】アルコールチェッカーおすすめ15選!運用法も徹底解説
関連記事:【2025年最新】業務用アルコールチェッカーおすすめ比較17選!選び方も解説
記録や運転日報を一元管理するアルコールチェッカーならセーフくん
 アルコールチェック義務化により企業の記録管理業務は大幅に増加し、従来の手作業では法令遵守と業務効率化の両立が困難です。
アルコールチェック義務化により企業の記録管理業務は大幅に増加し、従来の手作業では法令遵守と業務効率化の両立が困難です。
複雑化する記録要件と保存義務に対応するため、クラウドシステムによる自動化と一元管理が最適な選択肢です。手入力による転記ミスや紛失リスクを完全に排除し、法令で定められた1年間の保存義務も確実に履行できます。
「セーフくん」なら、運転日報とアルコールチェック記録の煩雑な管理業務をクラウド上で簡単に解決することが可能です。不正防止も徹底しており、リアルタイム監視で企業のコンプライアンス体制を強化します。記録業務の課題でお悩みの企業様は、この機会にぜひ導入をご検討ください。